「上の子の小学校入学と、下の子の幼稚園入園が重なる…!もしかして、3歳差だと入学式がかぶるの?!」
3歳差きょうだいの子育てを考えている、または現在進行形のママ・パパにとって、入園・入学式問題は大きな悩みの種ですよね。初めての経験であればなおさら、準備や当日のスケジュール、そして何より、大切な我が子の晴れ舞台にちゃんと出席できるのか…不安でいっぱいになるのも当然です。
3歳差育児にまつわる様々な疑問や不安を解消するための、具体的な情報と対策をお届けします。
さらに、3歳差育児を経験した先輩ママのリアルな体験談や、専門家のアドバイスも交えながら、あなたの3歳差育児を全力でサポート!
この記事を読めば、3歳差入学式がかぶる問題への不安が解消され、3歳差育児をスムーズに進めるためのヒントが見つかるはずです。さあ、一緒に3歳差育児の準備を始めましょう!
3歳差入学式かぶる問題!行事は?

「上の子の小学校入学と、下の子の幼稚園入園が同じ年…!入学式がかぶったらどうしよう…」3歳差きょうだいを持つママなら、一度はそんな不安を感じたことがあるのではないでしょうか。私も3歳差育児を経験し、入学式・入園式問題には頭を悩ませました。この記事では、3歳差育児のリアルな体験談と、専門家のアドバイスを交えながら、入学式・入園式問題、そして3歳差育児の大変さやその対策について、徹底的に解説していきます。この記事を読めば、入学式・入園式問題への不安が解消され、3歳差育児をスムーズに進めるためのヒントが見つかるはずです!
兄弟の入学式かぶる心配は?

3歳差の入学・入園問題、心配ですよね。でも大丈夫!事前に日程を確認して、うまく分担すれば、両方の晴れ舞台をしっかり見守ることができますよ。
結論からお伝えすると、同じ公立の幼稚園・小学校に通う場合、入学式・入園式の日程がかぶる心配はほぼありません。 なぜなら、多くの自治体では、3歳差のきょうだいがいる家庭が多いことを考慮し、入園式・入学式、そして卒園式・卒業式の日程を調整しているからです。
具体的には、
- 午前と午後で時間をずらす
- 別日に設定する
- 同じ日に実施する場合でも、開始時間をずらす
といった配慮がされています。
ただし、これはあくまでも公立の幼稚園・小学校の場合です。私立の幼稚園や小学校、または異なる自治体の学校に通う場合は、日程がかぶってしまう可能性もゼロではありません。
【確実に確認する方法】
- 各学校・園の年間行事予定を早めに確認する:多くの学校・園では、前年度の終わり頃(2月~3月)に次年度の年間行事予定を発表します。
- 直接問い合わせる:もし年間行事予定で確認できない場合は、直接学校・園に問い合わせてみましょう。
- 就学時健診・入園説明会で確認する。 就学時健診とは:小学校入学前の年の秋頃(10月~11月)に行われる健康診断のことです。 入園説明会とは:入園前の10月から2月頃に実施され、入園までの流れや必要なものなどの説明を受けます。
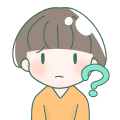
入学式と入園式がかぶった場合、どちらを優先すべきでしょうか?

どちらも大切な行事なので、まずは学校や園に相談し、日程の調整が可能か確認しましょう。それでもかぶってしまった場合は、夫婦で分担したり、祖父母に協力してもらうのがベストです。もしそれも難しければ、上の子の入学式を優先し、下の子の入園式には後日フォローをしっかりしてあげるといいですよ。
もし日程がかぶることが判明した場合は、
- 夫婦で分担して出席する
- 祖父母に協力を依頼する
- 上の子には、事情を説明して理解を求める
などの対策を、早めに検討しておきましょう。
3歳差育児で大変なことは何ですか?
3歳差育児で多くのママが大変だと感じるのは、上の子の赤ちゃん返りやイヤイヤ期と、下の子の新生児期が重なる時期です。
上の子は、今まで自分だけに向けてくれていたママの愛情が、下の子にも向けられることに、寂しさや不安を感じます。その結果、
- 赤ちゃん返り:今までできていたことができなくなる(例:自分で着替えができない、一人で食事ができない)
- イヤイヤ期:何をするにも「イヤ!」と反抗する
- 試し行動:わざと困らせるようなことをする(例:大声を出す、物を投げる)
といった行動が見られることがあります。
具体的なエピソード
- 下の子の授乳中に、「抱っこして!」「絵本読んで!」とせがまれ、ゆっくり授乳できない。
- 下の子のおむつ替え中に、「僕も!」「私も!」とおむつをつけたがる。
- 上の子の幼稚園の準備をしていると、「行きたくない!」とぐずりだす。
この時期は、ママも睡眠不足やホルモンバランスの乱れで、心身ともに疲れがピークに達していることも。無理をせず、周囲の協力を得ながら、乗り越えましょう。

3歳差育児の大変さは一時的なもの。上の子が成長すると、下の子のお世話を手伝ってくれることも!焦らず、周りの力を借りながら乗り越えましょう。
3歳差育児はしんどい?体験談
「3歳差育児はしんどい」という声は、インターネット上でもよく見かけます。実際に3歳差育児を経験したママたちのリアルな声を集めてみました。
- 幼稚園行事問題:「上の子の幼稚園の運動会に、下の子を連れて行くのが本当に大変でした。まだ歩けないので、ずっと抱っこ紐。しかも、上の子の出番を見逃さないように、常に気を張っていなければならず、ヘトヘトになりました。」(3歳女の子、0歳男の子のママ)
- 宿題問題:「上の子が小学校に入学したばかりの頃は、宿題を見てあげるのが大変でした。下の子はまだ幼稚園児なので、遊びたい盛り。上の子が宿題をしていると、必ず邪魔をしに来るんです。結局、下の子が寝た後に、上の子の宿題を一緒にやる…という毎日でした。」(6歳女の子、3歳男の子のママ)
- 食事問題:「上の子は好き嫌いが多く、下の子は離乳食。毎日、別々のメニューを作るのが本当に面倒でした。しかも、上の子は下の子の離乳食を、下の子は上の子の普通食を食べたがるんです…。」(5歳女の子、2歳男の子のママ)
これらの体験談からも分かるように、3歳差育児は、上の子と下の子の成長段階の違いから生じる、さまざまな「しんどさ」があります。
しかし、これらの「しんどさ」は、永遠に続くわけではありません。子どもの成長とともに、必ず楽になる日が来ます。先輩ママたちの体験談を参考に、自分なりの息抜き方法を見つけたり、便利な育児グッズを活用したりしながら、乗り越えていきましょう。
3歳差のデメリットは?
3歳差育児のデメリットとして、多くの方が懸念されるのが、経済的な負担です。
特に、教育費の負担は、家計に大きく影響します。
| イベント | 費用(目安) |
| 幼稚園入園準備費用 | 5万円~10万円 |
| 小学校入学準備費用 | 5万円~10万円 |
| 中学入学準備費用(制服など) | 5万円~10万円 |
| 高校入学金(私立) | 20万円~30万円 |
| 大学入学金(私立) | 30万円~50万円 |
上記の表からも分かるように、入園・入学のタイミングが重なると、一度に多額の出費が必要になります。
さらに、塾代や習い事の費用も加算されると、家計はさらに圧迫されます。
具体的な対策
- 学資保険:子どもの教育資金を計画的に準備できる
- 児童手当:中学校卒業までの子どもがいる家庭に支給される
- 自治体の子育て支援制度:各自治体独自の制度(例:医療費助成、保育料の軽減など)
これらの制度を積極的に活用し、経済的な負担を軽減しましょう。
3歳差受験被る問題とは

3歳差の受験がかぶると大変ですが、事前に計画を立てれば乗り越えられます!中高一貫校や推薦入試を活用するのも一つの手ですよ。
3歳差きょうだいの場合、上の子が高校3年生、下の子が中学3年生の時に、受験が重なる可能性があります。
この時期は、
- 塾代や受験料などの経済的な負担
- 精神的な負担
が、ピークに達します。
精神的な負担の例
- 上の子は、大学受験という人生の大きな岐路に立たされ、ピリピリしている。
- 下の子は、初めての受験で不安や緊張を感じている。
- 親は、両方のサポートをしなければならず、心身ともに疲弊する。
具体的な対策
- 上の子の中学受験を検討する:中高一貫校に進学すれば、高校受験がなくなるため、精神的な負担を軽減できる。
- 下の子の受験は、推薦入試やAO入試などを活用する:一般入試よりも早い時期に合否が決まるため、精神的な負担を軽減できる。
- 家族で話し合い、協力体制を築く:受験は、家族全員で乗り越えるべきイベントです。お互いを励まし合い、支え合うことが大切です。
- 塾のオンライン授業を活用する: 通塾の負担を減らす
3歳差入学式かぶる!事前準備と対策

3歳差きょうだいの入園・入学準備は、同時進行で進める必要があるため、計画的に行うことが大切です。ここでは、具体的な事前準備と対策について解説します。
子作り学年差計算アプリ活用
近年、子どもの年齢差を計画的に考えるための「子作り学年差計算アプリ」が登場しています。これらのアプリを活用することで、
- 希望する年齢差で子どもを授かるための、最適なタイミングを把握できる。
- 入園・入学、受験などのライフイベントが重なる時期を、事前にシミュレーションできる。
- 上の子と下の子それぞれの行事予定をカレンダーで管理できる
といったメリットがあります。
例えば、「3歳差で子どもを授かりたい」と考えた場合、アプリに上の子の生年月日を入力すると、下の子を妊娠するべき時期を自動的に計算してくれます。
ただし、アプリはあくまで目安であり、必ずしも計画通りに妊娠できるとは限りません。参考程度に活用し、過度な期待はしないようにしましょう。
3学年差メリットを活かすには
3学年差のメリットは、
- 幼稚園や小学校の行事が重なりにくい:運動会や発表会などの日程がずれていることが多いので、両方の行事に参加しやすい。
- 上の子が下の子の面倒を見てくれる:おむつ替えや着替えを手伝ってくれたり、一緒に遊んでくれたりする。
- 育児用品を効率的に使い回せる:ベビーカーやベビーベッド、チャイルドシートなど、上の子が使っていたものを下の子に譲ることができる。
- 上の子の時に購入した教材を共有できる:年齢に合わせた内容であれば、新たに買い足す必要がありません。
これらのメリットを最大限に活かすためには、
- 上の子に、下の子のお世話を積極的に手伝ってもらう
- 上の子が使っていた育児用品を、下の子のために保管しておく
- 上の子の成長に合わせて、下の子にも同じ習い事をさせる
といった工夫をしてみましょう。
3歳差はメリットだらけ?
「3歳差育児はメリットだらけ」という意見もありますが、実際にはデメリットも存在します。
メリット
- 育児期間が比較的短い
- 上の子が下の子の面倒を見てくれる
- 行事が一度に済む
デメリット
- 経済的な負担が大きい
- 上の子の赤ちゃん返りやイヤイヤ期と、下の子の新生児期が重なる
- 受験が重なる可能性がある
- 上の子の幼稚園、小学校の役員活動と下の子の育児が重なる
メリットとデメリットの両方を理解した上で、自分たち家族にとって最適な選択をすることが大切です。
3歳差デメリット対策を紹介
3歳差育児のデメリットを軽減するためには、
- 経済的な備え:学資保険や児童手当などを活用し、計画的に貯蓄をする。
- 上の子との時間:下の子のお世話で忙しい中でも、意識的に上の子との時間を作る。(例:一緒に絵本を読む、公園で遊ぶ、お風呂に一緒に入るなど)
- 夫婦の協力:家事や育児の分担を明確にし、協力体制を築く。
- 外部のサポート:祖父母、一時保育サービス、ファミリーサポート、ベビーシッターなどを積極的に利用する。
- 時短家電の導入: 食洗器、乾燥機付き洗濯機、ロボット掃除機など
- ネットスーパーや食材宅配サービスの利用
といった対策が有効です。
2歳差と3歳差どっちが多い?
一般的に、2歳差のきょうだいが多いと言われています。その理由は、
- 育児期間を短くしたい
- 上の子の赤ちゃん返りが落ち着く時期
- 経済的な負担を分散できる
などが挙げられます。
しかし、近年では、3歳差を選択する家庭も増えています。その背景には、
- 育児に余裕を持ちたい
- 上の子の成長をゆっくり見守りたい
- 仕事との両立をしやすい
といった理由があるようです。
どちらが良い、悪いではなく、各家庭の状況や考え方によって、最適な選択は異なります。
2人目は何歳差が多い?
厚生労働省の「令和3年度「出生に関する統計」の概況」によると、第1子出生時の母の平均年齢は30.9歳、第2子出生時の年齢差で最も多いのは、2歳差(28.5%)です。次いで、3歳差(25.1%)、1歳差(年子)(16.8%)となっています。
しかし、近年では、晩婚化や晩産化の影響もあり、4歳差以上(29.6%)のきょうだいも増えています。
3歳差Q&Aよくある質問
Q. 入学式と入園式が同じ日になったらどうすればいいですか?
A. まずは、それぞれの学校・園に相談してみましょう。多くの場合、時間帯をずらしたり、別日に設定したりするなどの配慮をしてくれます。もし、どうしても日程が調整できない場合は、夫婦で分担して出席する、祖父母に協力を依頼する、写真館で記念撮影だけ行うなどの対策を検討しましょう。
Q. 上の子の赤ちゃん返りがひどくて困っています。どうすればいいですか?
A. 赤ちゃん返りは、上の子が愛情不足を感じているサインです。下の子のお世話で忙しいとは思いますが、意識的に上の子との時間を作り、スキンシップを増やしましょう。「大好きだよ」「いつもありがとう」など、言葉で愛情を伝えることも大切です。また、下の子が生まれる前から、赤ちゃん返りやイヤイヤ期への心構えをしておくと、気持ちに余裕が持てます。
Q. 3歳差育児で、経済的に不安です。何か良い対策はありますか?
A. 学資保険や児童手当などを活用し、計画的に貯蓄をしましょう。また、自治体によっては、子育て支援制度が充実している場合もあります。お住まいの地域の情報を確認し、利用できる制度は積極的に活用しましょう。さらに、リサイクルショップやフリマアプリなどを活用し、育児用品を安く手に入れるのもおすすめです。
Q.上の子の幼稚園の役員と下の子の育児が重なって大変です。
A. 無理のない範囲で役員を引き受ける、どうしても難しい場合は正直に事情を説明して辞退することも検討しましょう。また、他の保護者に相談し、協力をお願いするのも一つの方法です。
Q.上の子の小学校入学準備と下の子の入園準備、何から手を付ければいいですか?
A. まずは、それぞれのスケジュールを確認し、いつまでに何をしなければならないかを把握しましょう。リストを作成し、優先順位をつけて、計画的に準備を進めるのがおすすめです。
3歳差育児のまとめ

まとめ
- 公立の幼稚園・小学校の場合、入学式・入園式がかぶる心配はほぼない
- 私立や異なる自治体の場合は、日程がかぶる可能性があるので早めに確認が必要
- 入学式・入園式が重なる場合、夫婦で分担、祖父母に協力依頼などの対策がある
- 3歳差育児は上の子の赤ちゃん返りやイヤイヤ期と新生児期が重なる大変さがある
- 3歳差育児の経済的負担は大きいが、学資保険や助成金で対策可能
- 上の子が高校3年生、下の子が中学3年生の時に受験が重なる可能性がある
- 3歳差のメリットは、育児用品を効率的に使い回せること
- 上の子が下の子の面倒を見てくれるなど、成長を助け合う場面がある
- 3歳差育児のデメリット対策として、夫婦の協力や外部サポートの活用が重要
- 子作り学年差計算アプリで、計画的な妊娠・出産をサポートできる
- 2歳差きょうだいが最も多いが、3歳差を選ぶ家庭も増えている
- 自治体の子育て支援制度を確認し、積極的に活用する
3歳差育児は、入学式・入園式の心配や経済的な負担など、気になる点も多いですが、事前の情報収集と準備で、多くの問題は解決できます。この記事で紹介した対策を参考に、3歳差育児のメリットを最大限に活かし、楽しい子育てライフを送りましょう!今すぐ、お住まいの地域の入学式・入園式情報をチェックし、早めの準備を始めることをおすすめします。


