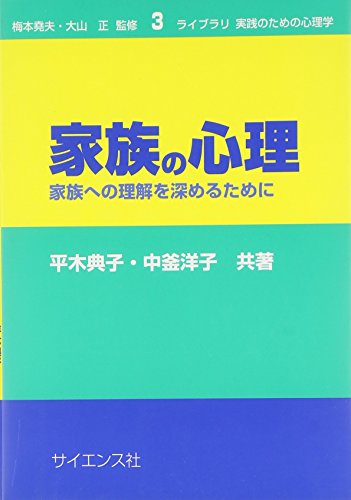「最近、高校生の息子の態度がまるで別人みたい…」 「前はあんなに素直だったのに、今は無視されたり、ひどい言葉をぶつけられたり… 私の育て方が間違っていたのかな?」
そして何より、多くの方が心の中で問いかけているのではないでしょうか。 「高校生反抗期男子いつまで続くの? この辛い状況に、本当に終わりは来るの?」
今、あなたはそのような出口の見えない不安や、どうしようもないほどの疲れを感じていらっしゃるかもしれませんね。毎日息子さんと顔を合わせることすら、億劫に感じてしまう日もあるでしょう。そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
でも、どうか安心してください。息子さんの反抗期は、決してあなたのせいではありません。そして、それはお子さんが「子ども」から「大人」へと成長するために、避けては通れない大切なプロセスの一部なのです。
この記事を読み終える頃には、きっとあなたの心の中にあるモヤモヤとした不安が少し晴れ、「そういうことだったのか!」という発見があるはずです。そして、反抗期の息子さんとこれからどう向き合っていけば良いのか、具体的な道筋が見えてくることを願っています。一人で抱え込まず、一緒に解決の糸口を探していきましょう。
高校生反抗期男子いつまで?基礎知識と特徴を知ろう

高校生の反抗期はいつまで?第二次反抗期とは
まず、一番気になる「いつまで続くの?」という疑問ですが、結論から言うと、高校生の反抗期が終わる時期には本当に個人差が大きいです。
一般的には、この時期の反抗期は「第二次反抗期」と呼ばれ、早い子では小学校高学年(11歳頃)から始まります。そして、多くの場合、高校生から大学生(17~20歳頃)にかけて、少しずつ落ち着いていくとされています。
第二次反抗期とは?
簡単に言うと、子どもが心の中で「親から精神的に自立したい!」「自分らしさを見つけたい!」と強く願い、自分自身の考え方や価値観(=自我・アイデンティティ)を確立しようとする時期のことです。ちょうど、心も体も大きく変化する「思春期」と重なるため、ホルモンバランスの影響も受けて、子ども自身もイライラしたり、感情が不安定になったりしやすい、とてもデリケートな時期なのです。
多くの場合、反抗期は「気づけば、いつの間にか終わっていた」と感じられることが多いようです。明確な「終了日」があるわけではなく、数年にわたって波があることも珍しくありません。
ですから、「うちの子はまだ反抗期が終わらない…」と焦る必要は全くありません。むしろ、反抗期があること自体は、お子さんが一人の人間として自立しようと頑張っている証拠。順調な成長のサインと捉えることもできるのです。大切なのは、期間の長さに一喜一憂せず、お子さんの成長段階を理解しようと努める姿勢と言えるでしょう。

“反抗期は自立の一歩”という視点で見ると、親の心構えも少しずつ変わってきますよ。
男子高校生の反抗期の特徴は?行動と言動の変化
高校生の男の子が見せる反抗期には、いくつかの共通した特徴があります。もちろん、お子さん一人ひとり違いますが、「うちの子もそうだ!」と思い当たることがあるかもしれません。
1. 親とのコミュニケーションを避ける
これが一番分かりやすい変化かもしれませんね。「別に…」「うるさい」「関係ないだろ」といった短い返事が増えたり、話しかけても露骨に無視したり…。以前はあんなにおしゃべりだった子が、急に口数が減って、自分の部屋に閉じこもりがちになることもあります。
これは、親からの干渉を避け、「自分のテリトリー」を守りたい、一人の人間として扱ってほしいという気持ちの表れと考えられます。
2. 言葉遣いや態度が荒っぽくなる
イライラした感情をうまくコントロールできず、乱暴な言葉遣いになったり、物に当たったり、ドアをバタン!と強く閉めたり…。特に男の子の場合、感情を言葉で表現するのが苦手で、衝動的な行動や暴言として表に出やすい傾向があると言われています。体つきも大人に近づき、親として威圧感を感じてしまうこともあるかもしれません。
3. 無気力に見えることも
急に身だしなみに無頓着になったり、逆に過剰にこだわり始めたり。大好きだったはずの部活動や、以前は頑張っていた勉強への意欲が低下してしまうこともあります。これは、自分の内面(「自分って何だろう?」)や将来への不安など、目に見えない部分で悩み、エネルギーを消耗しているサインかもしれません。
これらの行動や言動を見ると、親としては心配になったり、時にはカチンときたりしますよね。でも、これらの多くは、お子さんが「自立」という大きな壁にぶつかり、もがいている証拠なのです。その行動の表面だけを見るのではなく、「この態度の裏にはどんな気持ちがあるんだろう?」と、少し立ち止まって考えてみることが、反抗期の対応の第一歩になります。
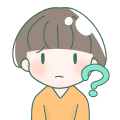
息子の暴言にどうしても感情的になってしまいます…。冷静に対応するにはどうしたらいいですか?

その気持ち、よく分かります。私もよくカチンときましたよ(笑)。でも、一呼吸置いて“この子は今、自分の中で何と戦ってるのかな?”と考えるクセをつけると、少しずつ対応が変わってきました。
男の子の反抗期ピークはいつ頃?目安の時期
「最近、息子の反抗的な態度が特にひどい気がする… これがピークなのかな?」と、嵐の中心にいるような気持ちになることもありますよね。男の子の第二次反抗期のピーク時期も、やはり個人差が大きいのですが、一般的には中学生から高校生にかけて迎える子が多いと言われています。
特に、中学2年生頃は、心も体も大きく変化し、自我意識も強まるため、反抗的な態度が最も強く表れやすい時期のひとつ。「中2病」なんて言葉もありますが、実際にこの時期に、多くの親御さんが反抗期の対応に頭を悩ませています。
もちろん、高校生になってから反抗期のピークを迎える子もたくさんいます。逆に、中学生のうちにピークを過ぎて、高校生になると少しずつ落ち着きを取り戻す子も。男子の場合、女子に比べて反抗期の始まりが遅い傾向があるため、ピークが高校生の時期にずれ込むことも珍しくありません。
ここで大切なのは、「ピークはいつか」を正確に知ることよりも、「反抗的な態度が強まっている時期 = 子どもが内面で大きな葛藤を抱えている時期」だと理解することです。
「大人になりたい自分」と「まだ未熟な自分」の間で激しく揺れ動き、本人もどうしたら良いか分からなくなっているのかもしれません。
このピーク時期は、親も感情的になりやすいもの。ですが、意識して冷静さを保つことが、親子関係をこじらせないために非常に重要です。「売り言葉に買い言葉」でぶつかるのではなく、お子さんの気持ちを受け止めつつ、少し距離を置いて見守る。そんな「大人の対応」が求められる時期と言えるでしょう。ピークが過ぎれば、必ず状況は変化していきます。
女子の反抗期の特徴は?男子との違いを比較
反抗期の表れ方には、性別による傾向の違いも見られます。もちろん、「男の子だからこう」「女の子だからこう」と一概には言えませんが、一般的な違いを知っておくと、息子さんの状況をより客観的に捉えるヒントになるかもしれません。
これまで見てきたように、男の子の反抗期は、内に秘めた感情が行動や暴言として表に出やすい傾向があります。物に当たったり、言葉遣いが荒くなったり、時には親に対して挑戦的な態度を取ったり…。感情を整理して言葉にするのが苦手な分、衝動的に外側へ発散させてしまうことがあるのです。
一方、女の子の反抗期は、言葉による反発や無視といった形で現れることが多いと言われています。
- 口答えが増える
- 親の意見に理屈で言い返す
- 冷たい態度で親を突き放す
- ため息や舌打ちが増える
といった行動が見られがちです。また、友人関係でのいざこざや悩みを家庭に持ち込み、家族に対してイライラした態度を取ることも少なくありません。感情の細やかな動きに敏感で、親のちょっとした言葉に過敏に反応してしまうこともあります。
時期についても違いが見られ、一般的には女の子の方が男の子よりも早く反抗期が始まり、早く終わる傾向にあります。小学校高学年から反抗的な態度が見られる女の子も珍しくありません。
ただし、これはあくまで統計的な傾向です。男の子でも、冷静に言葉で反論するタイプの子もいますし、女の子でも、行動で不満を示す子もいます。一番大切なのは、性別で判断するのではなく、目の前にいる「我が子」の個性と、その言動の背景にある気持ちをしっかりと見つめ、理解しようとすることです。
高校生で反抗期はおかしい?遅い反抗期について
「周りの子の反抗期は落ち着いてきたみたいだけど、うちの子は高校生になってからが本番みたいで…」「もしかして、うちの子だけおかしいのかな?」
そんな風に不安を感じてしまう親御さんもいるかもしれませんね。でも、安心してください。高校生になってから反抗期が始まること、あるいは高校生になっても反抗期が続くことは、決して「おかしい」ことではありません。むしろ、現代ではよく見られるケースの一つと言えます。
反抗期が始まる時期や続く期間には、本当に大きな個人差があります。高校生という、いわゆる「遅い」タイミングで反抗期が始まる(または続く)背景には、いくつかの理由が考えられます。
1. 我慢の限界
それまで「良い子」でいようと、親の期待に応えようと頑張ってきた子が、心の中に溜め込んできた不満や「本当はこうしたい」という気持ちが、我慢の限界を超えてあふれ出すケースです。特に、親が進路や友人関係、趣味などに強く干渉してきた場合、子どもは自分の本音を抑え込んできた可能性があります。高校生になり、自我がよりはっきりとしてきた段階で、抑圧された感情が反抗という形で噴出するのです。
2. 環境の変化
高校進学は、子どもにとって大きな環境の変化です。新しい友人関係、中学よりも格段に難しくなる勉強、迫りくる進路選択へのプレッシャー、部活動での人間関係など…。これらの様々なストレスが引き金となり、それまで見られなかった反抗的な態度が現れることがあります。
3. 自己主張の練習
もともと大人しい性格の子が、社会に出る準備段階として、意識的に自己主張の練習を始めるケースもあります。一番身近で、何を言っても最終的には受け入れてくれる(と信じている)親に対して、まず自分の意見をぶつけてみよう、と試しているのかもしれません。
「遅いから心配」と捉えるのではなく、「この子なりのタイミングで、自立へのステップを踏み始めたんだな」と、少し長い目で見守ってあげることが大切です。
高校生の反抗期が遅いと感じる背景
前述の通り、高校生になってから反抗期が始まる、または続くのは、決して異常なことではありません。「うちの子は他の子より遅いのでは?」と感じる背景には、お子さん自身の個性や、これまでの親子関係、家庭環境などが深く関わっています。いくつか具体的な背景を見ていきましょう。
1. お子さんの性格・気質
元々、おっとりしていて自己主張が控えめな性格のお子さんの場合、反抗的な感情を表に出すまでに時間がかかることがあります。心の中では色々なことを感じていても、それを言葉や態度で表現するのが苦手で、内に溜め込んでしまうタイプです。そして、思春期後半になり、友人関係や社会との関わりの中で「自分の意見を言わなければならない」場面が増え、自己主張の必要性を強く感じた時に、初めて反抗という形で現れることがあります。これは、時間をかけて自分と向き合い、自立への重要な一歩を踏み出そうとしている証拠とも言えます。
2. 安定した親子関係
意外かもしれませんが、親子関係が非常に良好で、お子さんが親に対して深い安心感を抱いている場合、あえて強く反抗する必要性を感じずに成長することがあります。しかし、高校生になり、様々な価値観に触れる中で、「親の言うことが全てではない」「自分自身の考えを持ちたい」と感じ始めるのは自然なことです。その過程で、これまで絶対的な存在だった親に対して、健全な疑問や批判的な視点を持つようになり、それが反抗的な態度として表れることがあります。これは、親への依存から抜け出し、精神的に自立しようとする健全なプロセスなのです。
3. 家庭環境の影響
例えば、下に幼い兄弟がいて親の関心がそちらに向きがちだった、親が仕事で非常に忙しかった、あるいは夫婦関係に緊張があったなど、お子さんが「甘えたい」「構ってほしい」という気持ちを十分に満たされずに成長してきた場合、その寂しさや不満が、高校生になってから反抗という形で現れることもあります。
「遅い」と感じても、それはお子さんなりの成長のペースです。その背景にある理由を探ろうと焦るのではなく、今、目の前で変化しようとしているお子さんの姿を受け止め、寄り添う姿勢が大切になります。

“この子なりのタイミング”を信じて待つ。それが、一番難しくて、一番大切なことかもしれませんね。
高校生反抗期男子いつまで続く?終わりのサインと親の関わり方

ここまで、高校生男子の反抗期の特徴や、それが始まる背景について詳しく見てきましたね。
「反抗期の仕組みは分かったけど、じゃあ、この状況はいつまで続くの?終わりは本当に来るの?」
そして、「イライラしたり、無視されたりする息子に、具体的にどう接したらいいの?」
そんな切実な疑問が、今あなたの心を占めているかもしれません。
このセクションでは、皆さんが一番知りたいであろう、反抗期が終わる一般的な時期やきっかけ、そして希望の光となる「終わりのサイン」について解説します。
さらに、反抗期対応に疲れてしまった時の具体的な対処法や、親子関係をこじらせずにこの時期を乗り越えるための効果的な接し方についても、実践的なアドバイスをお届けします。
反抗期の真っ只中にいると、出口が見えないように感じるかもしれません。でも、大丈夫です。適切な関わり方を根気強く続けることで、必ず状況は良い方向へ向かっていきます。希望を持って、具体的な方法を一緒に見ていきましょう。
高校生の反抗期はいつ終わる?一般的な期間
「結局のところ、高校生の反抗期って、いつになったら終わるの?」
反抗期に悩む親御さんにとって、これは本当に切実な問いですよね。何度も触れてきましたが、「この日になったら終わります」という明確な日付はありません。お子さん一人ひとり、ペースが全く違います。
しかし、一般的な傾向として、多くの場合、高校卒業から大学進学、あるいは就職など、社会へ出る準備を本格的に始める【18歳前後】が一つの節目となり、反抗的な態度が和らいでいくケースが多いようです。
なぜこの時期なのでしょうか?
それにはいくつかの理由が考えられます。
- 精神的な成熟: この頃になると、子ども自身が精神的にかなり成長し、自分の考え方や価値観(アイデンティティ)がある程度、形になってきます。むやみに反発するのではなく、自分と他者の違いを認められるようになってくるのです。
- 将来への見通し: 進路選択という大きな決断を乗り越え、「大学でこれを学びたい」「こんな仕事に就きたい」といった具体的な目標が見えてくることで、精神的な安定感が増します。目の前の目標に集中するため、親に反抗するエネルギーが減ることもあります。
- 環境の変化: 親元を離れて一人暮らしを始めたり、大学や専門学校という新しい環境に身を置いたりすることで、物理的にも精神的にも親との距離が生まれます。客観的に親子関係を見つめ直す機会となり、親のありがたみを実感するなどして、反抗期が自然と終わりを迎えるきっかけになることも多いのです。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。「うちの子は18歳を過ぎてもまだ反抗期が…」と感じる場合でも、焦る必要はありません。反抗期が長引く背景には、親子関係のこじれや、本人が抱える別の悩みなどが隠れている可能性もあります。
大切なのは、「いつ終わるか」という時期ばかりを気にするのではなく、反抗期の終わりには【子どもの内面的な成長】と、それを支える【親子関係の質】が深く関わっていると理解することです。根気強く、お子さんの成長を見守り続ける姿勢が何よりも重要になります。
反抗期が終わるきっかけ:子の成長と環境変化
反抗期の終わりは、まるでスイッチが切り替わるように突然訪れるわけではありません。多くの場合、いくつかの「きっかけ」が重なり、子どもの内面的な成長や環境の変化によって、徐々に終わりに向かっていきます。では、具体的にどんなことがきっかけになるのでしょうか?
1. 自我(アイデンティティ)の確立
これが最も本質的なきっかけです。「自分とは何者か」「自分はどう生きたいか」といった問いに向き合い、自分自身の価値観や考え方を確立できると、他者(特に親)との違いを認められるようになります。むやみに反発することで自分を主張する必要がなくなり、精神的に安定していきます。これは、様々な経験や内面の葛藤を乗り越えた、大きな成長の証です。
2. 良好な親子関係の再構築
反抗期は、親子関係を見直す時期でもあります。子どもが「親は自分のことを理解し、一人の人間として尊重してくれている」と感じられるようになると、反抗する理由が減っていきます。親が子どもの話をしっかり聞き、共感し、頭ごなしに否定しない姿勢を示すことが、信頼関係の再構築に繋がり、反抗期の穏やかな終息を促します。
3. 将来の目標や夢の発見
「大学でこれを学びたい」「こんな仕事に就きたい」「〇〇を実現したい」といった具体的な目標が見つかると、それに向かって努力する必要性を感じ、責任感や自覚が芽生えます。「親に反抗している場合じゃない」と意識が切り替わり、反抗的な態度が影を潜めることがあります。
4. 大きな成功体験・失敗体験
部活動でのレギュラー獲得や大会での活躍、難関校への合格といった成功体験は、大きな自信に繋がります。逆に、受験の失敗、失恋、友人関係での深い悩みといった挫折体験も、それを乗り越える過程で人間的に大きく成長させます。これらの経験が、反抗期を卒業するきっかけとなることも少なくありません。
5. 環境の大きな変化
一人暮らしを始めたり、留学したり、あるいは親しい人との別れや新しい出会いなど、生活環境がガラッと変わることも大きなきっかけになります。特に親元を離れると、物理的な距離ができ、客観的に自分や家族のことを見つめ直す機会が生まれます。「親のありがたみが分かった」という話は、この典型例ですね。
これらのきっかけは、お子さんによって様々です。共通しているのは、どれもお子さんが悩み、考え、経験を通して成長し、自立へと向かうための大切なステップであるということです。
反抗期の終わりのサインを見逃さないで
「最近、息子がちょっと変わってきたかも…? もしかして、反抗期の終わりが近い?」
そんな風に、お子さんの変化を感じ取る瞬間が訪れるかもしれません。反抗期は、ある日パタッと終わるのではなく、多くの場合、少しずつ態度が柔らかくなっていく形で終わりに向かいます。その微妙な変化、つまり「終わりのサイン」に気づけると、親としてもホッとしますし、今後の関わり方を考える上で大きな希望になりますよね。
サインに気づくことには、いくつかのメリットがあります。
- 親の気持ちが楽になる: 「終わりが見えてきた」と感じることで、精神的な負担が軽くなります。
- 適切な対応ができる: 子どもの変化に合わせて、親も関わり方を少しずつ変えていくことができます。
- スムーズな終息を後押し: 子どもの前向きな変化を認め、励ますことで、反抗期からの「卒業」をスムーズに後押しできる可能性があります。
例えば、こんな変化はありませんか?
- 以前は無視や「別に…」ばかりだったのが、日常的な会話が少しずつ増えてきた。
- 話しかけた時に、ちゃんと目を見てくれるようになった。
- 親の意見に対して、以前ほど感情的に反発しなくなった。
- 家族と一緒にいる時間が、少し増えた気がする。
これらのサインは、お子さんが精神的に安定を取り戻し、親との間に再びポジティブな関係を築こうとしている証拠かもしれません。
ただし、注意点もあります。思春期はただでさえ気分の波が激しい時期です。一時的に機嫌が良いだけ、という可能性も考えられます。ですから、数日〜数週間の少し長いスパンで様子を見て、「良い変化」が安定して続いているかどうかを見極めることが大切です。焦らず、お子さんの小さな変化に気づいてあげられると良いですね。

『ただいま』の一言が増えただけでも、親としては嬉しくて泣けちゃう瞬間ですよね。小さな変化を大事にしていきましょう。
具体的な反抗期が終わるサインは?チェック項目
では、具体的にどのような変化が見られたら、「反抗期の終わりが近いかも?」と考えられるのでしょうか。日々の生活の中でチェックできるポイントをいくつか挙げてみます。
お子さんの様子を思い浮かべながら、当てはまるものがあるか見てみてくださいね。
【コミュニケーションの変化】
- 親からの質問に、以前より素直に答える場面が増えた。
- 自分から学校や部活、友達のことなどを話してくれるようになった。
- 「ありがとう」「ごめん」といった言葉が、以前より自然に出てくるようになった。
- 親の話やアドバイスを、感情的にならずに聞ける時がある。 会話中に笑顔が増えたり、冗談を言い合ったりできるようになった。
【態度・行動の変化】
- ライラした様子や、物に当たるような行動が目に見えて減った。
- 表情が以前よりも穏やかになったと感じる。
- 食事の時間など、家族と一緒に過ごそうとする様子が見られる。
- 自分の部屋に閉じこもっている時間が減った。
- 頼んだお手伝いを、文句を言わずにやってくれることがある。
- 服装や髪型など、身だしなみに以前より気を遣うようになった。
- 部屋の片づけなど、整理整頓を自分からするようになった。
- 夜更かしが減るなど、生活リズムを整えようとしている。
【将来への意識の変化】
- 将来の夢や進路について、真剣に考えたり、相談してきたりするようになった。
- 勉強や部活動、アルバイトなど、目標に向かって努力する姿が見られる。
いかがでしたか?
これらの項目に当てはまるものが少しずつ増えてきたら、それはお子さんが精神的に大きく成長し、反抗期という長いトンネルの出口に確実に近づいているサインです。結果を急がず、温かい気持ちで、その成長を見守ってあげてください。
高校生の反抗期に疲れたと感じる親御さんへ
毎日、毎日、反抗的な態度をとる息子さんとの関わり…。
「もう、本当に疲れた…」
「私の気力も限界…」
そんな風に、心がすり減ってしまう感覚を覚えるのは、決してあなただけではありません。むしろ、それだけ一生懸命、愛情を持ってお子さんと向き合ってきた証拠です。どうか、ご自分を責めないでくださいね。
反抗期対応で疲れ切ってしまわないために、まず一番大切にしてほしいのは、あなた自身の心と体です。「親なんだから、頑張らないと」と、一人で全てを抱え込む必要はありません。
1. 少し肩の力を抜いてみましょう
「反抗期は成長に必要な時期なんだ」「いつかは終わるんだ」と、ある程度割り切る気持ちを持つことも大切です。完璧な親を目指さなくても大丈夫。
2. 意識的に「自分の時間」を作りましょう
週に1回、いえ、1日30分でも良いのです。
- 好きな音楽を聴く
- 温かいお茶をゆっくり飲む
- 好きな香りのアロマを焚く
- 短い時間でも散歩に出かける
- 湯船にゆっくり浸かる
- 友人とおしゃべりする(電話やオンラインでも!) など、あなたが「ホッ」とできる時間を意識的に作ってみてください。
3. 家事の「手抜き」もOK!
毎日完璧に家事をこなさなくても大丈夫。
- たまにはお惣菜や冷凍食品、デリバリーを活用する。
- 週末に作り置きをする。
- 便利な家電(食洗機、ロボット掃除機など)を導入する。
- 地域の家事代行サービス(シルバー人材センターなど、比較的安価な場合も)を調べてみる。 など、負担を減らす工夫を取り入れてみましょう。
4. 誰かに「話す」こと
これがとても重要です。溜め込んだ気持ちを吐き出すだけで、心は軽くなります。
- パートナー: もし協力が得られるなら、一番の味方です。現状や気持ちを共有しましょう。(もし協力が難しい状況でも、他の方法があります!)
- 友人・ママ友: 同じような経験を持つ友人の話は、共感やヒントに繋がります。
- 自分の親や兄弟姉妹: 気心の知れた家族に頼るのも良いでしょう。
- 専門家・相談窓口: 学校の先生やカウンセラー、地域の相談窓口など、客観的なアドバイスやサポートが得られます。(次の項目で詳しく紹介します)
あなたが笑顔でいることが、結局は家庭全体の明るさに繋がり、お子さんの心の安定にも良い影響を与えます。どうか、自分を大切にすることを忘れないでくださいね。

“私ばかりが頑張ってる…”そう感じたら、自分をいたわる時間を少しだけでも取ってあげてくださいね。
反抗期男子へのNG対応と効果的な接し方
反抗期の息子さんとの関わり方で、一番避けたいのは、親子関係が修復できないほどこじれてしまうことです。良かれと思ってしたことが、逆効果になってしまうことも…。ここでは、ついやってしまいがちな「NG対応」と、関係を悪化させずに乗り切るための「効果的な接し方」のポイントを、より具体的に見ていきましょう。
【これは避けたい!NG対応】
- 頭ごなしの否定・命令:
- 「何言ってるの!ダメに決まってるでしょ!」
- 「いいから、さっさと宿題しなさい!」
- → 子どもは聞く耳を持たず、さらに反発するだけです。
- 感情的な叱責・人格否定:
- カッとなって大声で怒鳴る。
- 「本当にあなたはダメな子ね!」
- 「お前なんか生まれてこなければよかった!」(これは絶対にNG!)
- → 心に深い傷を残し、信頼関係は崩壊します。
- 過干渉・プライバシー侵害:
- スマホを勝手に見る。
- 部屋に無断で入る。
- 友達関係や行動を根掘り葉掘り聞く。
- → 「信用されていない」と感じ、心を閉ざしてしまいます。
- 無視・放置:
- 腹が立つからと口をきかない。
- 「もう勝手にしなさい」と突き放す。
- → 「見捨てられた」と感じ、孤独感を深め、非行などに繋がるリスクも。
- 他の子(兄弟含む)との比較:
- 「お兄ちゃんはもっとちゃんとやってたよ」
- 「〇〇君は成績が良いのに…」
- → 子どもの自己肯定感を著しく低下させます。
【心がけたい!効果的な接し方】
- 「子ども扱い」をやめ、「一人の人間」として尊重する:
- 上から目線ではなく、対等な立場で話すことを意識する。
- 意見を求めたり、相談するような形をとるのも有効です。
- まずは「聴く」ことに徹する:
- 子どもの言い分や気持ちを、途中で遮らずに最後まで聞く。
- 「うんうん」「そうか」と相槌を打ち、「あなたの気持ちは分かったよ」と共感の姿勢を示す。(同意する必要はありません)
- 具体例: 「ゲームばかりしないで!」ではなく、「何かゲームに夢中になる理由があるの?」と聞いてみる。
- 冷静さを保つ:
- イラッとしたら、深呼吸する、その場を一旦離れるなど、感情的にならない工夫を。
- 適度な距離感を保つ:
- 干渉しすぎず、かといって無関心でもなく。「見守っているよ」「困ったらいつでも力になるよ」というスタンスで。
- 「私」を主語にして伝える(アイメッセージ):
- 「(あなたは)早く帰りなさい!」ではなく、「(私は)帰りが遅いと心配だよ」。
- 「(あなたは)部屋を片付けなさい!」ではなく、「(私は)部屋がきれいだと気持ちがいいな」。
- 言葉以外の方法で愛情を伝える:
- 会話が少なくても、食事で好物を作る、清潔な服を用意するなど、行動で「大切に思っている」気持ちを示す。
- 家庭内のルールは、一緒に決めて守る:
- 門限、スマホの時間、お金の使い方など、守るべき最低限のルールは、一方的に押し付けるのではなく、理由を説明し、子どもの意見も聞きながら一緒に決め、毅然と守らせる。
これらの接し方は、すぐに効果が出るものではないかもしれません。でも、根気強く続けることで、少しずつ関係性は変わっていくはずです。親子関係の改善を目指しましょう。
Q&A よくある質問
ここでは、高校生の反抗期に関して、親御さんから特によく聞かれる質問とその答えをまとめました。
Q1. 反抗期が全くないようなのですが、大丈夫でしょうか?心配です。
A1. 前述の通り、反抗期が目立たないお子さんもいます。一概に「問題がある」とは言えません。元々の性格や、親子関係が良好で自己主張しやすい環境である可能性も高いです。
ただし、注意したいのは、親に気を遣いすぎて本音を言えず、不満やストレスを溜め込んでいるケースです。この場合、後になって心の問題として現れたり、社会に出てから人間関係でつまずいたりする可能性も指摘されています。
チェックポイントとしては、
- お子さんが自分の意見や気持ちを普段から話せているか?
- 親の顔色をうかがうような様子はないか?
- 失敗したり、うまくいかなかったりした時に、それを話せるか? などを観察してみてください。もし心配な点があれば、お子さんが安心して本音を話せるような関わりを意識したり、必要であればスクールカウンセラーなどに相談してみるのも良いでしょう。
Q2. 父親は反抗期の息子にどう関わればいいですか?母親任せになりがちで…。
A2. これは非常に重要なポイントですね。特に男の子の場合、同性である父親の存在や関わり方が、反抗期を乗り越える上で大きな意味を持つことがあります。
- 母親と連携する: まずは夫婦で現状や悩みを共有し、対応方針を話し合うことが大前提です。「母親任せ」ではなく、チームとして関わる意識を持ちましょう。
- 母親のサポート役になる: 母親が感情的になった時に冷静になだめたり、話を聞いて共感したりするだけでも、母親の精神的な支えになります。
- 息子との「男同士」の関係を築く: 母親とは違う視点での関わりが有効な場合があります。例えば、共通の趣味(スポーツ、ゲーム、音楽など)を通してコミュニケーションをとる、少し遠出してみる、将来の話をしてみるなど。干渉しすぎず、でも頼れる存在として、適度な距離感で関わることが大切です。
- 社会の厳しさやルールを伝える役割: 母親が共感的な役割を担うのに対し、父親が社会性やルール、責任といった側面を教える役割を担うことも有効です。ただし、権威的に押さえつけるのではなく、対話を通して伝えることが重要です。
Q3. 反抗期で勉強しなくなってしまいました。受験も近いのに心配です。
A3. 「勉強しなさい!」が逆効果なのは、もうお分かりですよね。まずは学習意欲低下の原因を探ることが大切です。
- 他に熱中していることがある(部活、趣味、友人関係など)
- 勉強内容が難しくてついていけない
- 将来の目標が見えず、勉強する意味を感じられない
- 心身の不調や、別の悩みを抱えている などが考えられます。 対応としては、
- 本人の気持ちを聞く: なぜ勉強に身が入らないのか、じっくり話を聞いてみましょう。
- 勉強の意義を一緒に考える: 将来の夢や目標と勉強を結びつけ、「何のために勉強するのか」を本人が納得できるようサポートします。
- 環境を整える: 集中できる学習スペースを用意したり、塾や家庭教師など外部の力を借りたりするのも有効です。信頼できる第三者のアドバイスが効果的なこともあります。
- 小さな成功体験を積ませる: スモールステップで目標を設定し、「できた!」という達成感を味わえるようにサポートしましょう。
Q4. どこに相談すれば良いか、具体的に教えてください。
A4. 一人で悩まず、専門家や相談機関を頼ることはとても大切です。
- 学校: 担任の先生、学年主任、養護教諭(保健室の先生)、スクールカウンセラー。まずは一番身近な相談相手です。
- 自治体の相談窓口: 「〇〇市 教育相談」「〇〇県 子育て支援センター」「青少年センター」などで検索すると、お住まいの地域の窓口が見つかります。無料で相談できる場合が多いです。
- 児童相談所: 虐待だけでなく、子育てに関する様々な相談に応じてくれます。「189」(いちはやく)にかけると、近くの児童相談所につながります。
- 医療機関: 思春期外来、児童精神科、小児科など。心身の不調が伴う場合や、発達に関する心配がある場合に相談できます。
- 民間のカウンセリング: 臨床心理士など専門家によるカウンセリングが受けられます(有料の場合が多い)。
- NPO法人など: 子育て支援を行っている団体もあります。
どこに相談したら良いか迷う場合は、まずはお住まいの自治体の相談窓口や学校に問い合わせてみるのが良いでしょう。
まとめ:反抗期は成長の証、焦らず見守りましょう

今回は、多くの親御さんが頭を悩ませる「高校生男子の反抗期」について、その期間、特徴、終わりのサイン、そして親としての関わり方のヒントを詳しくお伝えしてきました。
高校生の反抗期(第二次反抗期)は、一般的に【高校卒業から大学生くらいまで】に落ち着くことが多いものの、その時期や長さは【お子さん一人ひとり全く違う】ということを、まず心に留めておいてください。「いつ終わるんだろう」と焦る気持ちは痛いほど分かりますが、反抗期は【お子さんが大人へと自立していくための、必要で大切なプロセス】なのです。
無視されたり、暴言を吐かれたり…そんな反抗的な言動の裏には、「本当は自分を認めてほしい」「親から干渉されたくない」「でも、将来が不安でどうしたらいいか分からない」といった、お子さん自身の複雑な心の葛藤が隠れています。
反抗期のトンネルには、必ず終わりがあります。お子さんの「終わりのサイン」に気づき、その成長を喜びながら、焦らず、根気強く、そして愛情を持って見守り続けていきましょう。この記事が、今まさに反抗期のお子さんと向き合っているあなたの不安を少しでも和らげ、前向きな気持ちで日々を過ごすための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
まとめ
- 高校生の反抗期が終わる明確な時期はなく個人差が大きい
- 反抗期は子どもが精神的に自立するための自然な成長過程
- 男子高校生の反抗期は行動や暴言に表れやすい傾向がある
- 高校生から始まる、あるいは続く遅い反抗期も珍しくない
- 反抗的な態度の裏には子どもの葛藤や成長欲求が隠れている
- 親は感情的にならず、子どもの話をまず聴く姿勢が重要
- 過干渉や頭ごなしの否定は親子関係を悪化させる
- 反抗期の終わりには会話の増加や態度の軟化といったサインがある
- 自我の確立や環境の変化などが反抗期終息のきっかけとなり得る
- 親自身も休息をとり、一人で抱え込まず外部に相談することも大切
- 具体的な接し方を学び実践することが関係改善の鍵となる