お子さんが学校に行けなくなり、出席日数や勉強の遅れについて、一人で悩んでいませんか。
先の見えないトンネルの中にいるような気持ちで、将来への不安に夜も眠れない日があるかもしれません。この記事では、不登校のお子さんを持つご家庭に向けて、在宅学習で出席扱いが認められるICT教材の制度や、お子さんに合った教材の選び方を、同じ経験を持つ筆者が、心を込めて丁寧に解説します。
【この記事の要点】不登校のお子さんの学習と出席日数の悩みを解決する一つの方法として、ICT教材の活用があります。文部科学省の制度を利用すれば、自宅での学習が学校の出席として認められる可能性があります。数ある教材の中でも、特に多くのご家庭で出席扱いの実績がある「すらら」は、まず検討したい選択肢です。
| 特に検討したい選択肢 | 主な理由 |
|---|---|
| オンライン教材「すらら」 | 1,700人以上の出席扱い実績があり、学校への説明もしやすい。 |
| その他の選択肢 | 進研ゼミなど、大手ならではのサポートが充実した教材も有効。 |
不登校でも大丈夫!ICT教材が出席扱いになる制度とは?

「このままずっと学校に行けなかったら…」そんな不安で、胸が押しつぶされそうになっていませんか。
「家で勉強しても、学校の出席にはならない」と思い込んでいる方も多いかもしれませんが、今は国が後押しする形で、自宅でのICT学習が学校の出席として認められる制度が整いつつあります。
この制度は、学校に戻ることだけをゴールとせず、お子さんが自分らしく学び、社会的に自立していくことを応援するためのもの。まずは正しい情報を知ることが、不安を和らげる第一歩になります。
増え続ける不登校と、文部科学省が示す新しい学びの形
背景には、不登校の児童生徒が過去最多を更新し続けているという、日本の教育現場が直面する現実があります。文部科学省の調査によると、令和4年度の小中学生の不登校者数は約30万人にのぼり(※1)、これは決して特別なことではありません。
こうした事態を受け、文部科学省は2019年に重要な通知を出しました(※2)。それは、一定の要件を満たせば、ICT等を活用した家庭学習を「出席扱い」と認めてよい、というもの。これは、学びの場を学校だけに限定せず、多様な学習機会を保障しようという国の強い意志の表れと言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 不登校児童生徒数 | 約29.9万人(令和4年度)過去最多 |
| 国の基本方針 | ICT等を活用した家庭学習を「出席扱い」として認める |
| 制度の目的 | 学校復帰だけでなく、児童生徒の社会的自立を支援する |
(※1 出典: 文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)
(※2 出典: 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」)
先輩ママの体験談「道は一つじゃない」から学べること
実は、この記事を書いている私自身も、二人の子育てで全く違う壁にぶつかった経験があります。
上の子は成績不振から親子二人三脚で猛勉強し、偏差値を大きく伸ばすことができました。しかし、下の子は学校という環境そのものが合わず、不登校に。上の子で成功したはずの方法は、全く通用しませんでした。
最初は「なぜうちの子だけ…」と途方に暮れましたが、通信制の学校という道を選び、在籍校と粘り強く交渉して「出席扱い」を認めてもらえた時、目の前がぱっと明るくなるのを感じました。
「みんなと同じ道」でなくても、その子がその子らしく輝ける場所は必ずある。それを実感した瞬間です。この経験から得た知識と実感が、今まさに悩んでいるご家庭の助けになればと心から願っています。
出席日数と学習の遅れ…中学生の親が抱える将来への不安
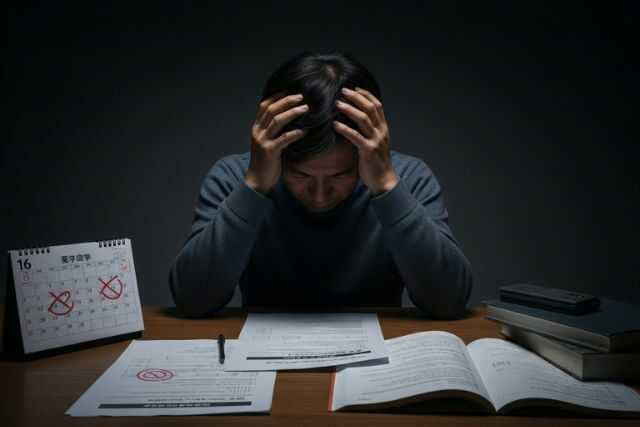
お子さんのことを思うほど、頭をよぎるのは「将来」のこと。特に中学生となると、高校受験という現実的な問題も相まって、その不安は日増しに大きくなっていくものですよね。
ここでは、多くの保護者の方が共通して抱える悩みを整理しながら、なぜICT教材がその解決策となり得るのかを、一緒に考えていきたいと思います。
高校受験に響く?内申点と出席日数の知られざる関係
中学校生活における出席日数は、高校入試で用いられる「内申点(調査書点)」に直接影響することがあります。ご存知の通り、多くの都道府県では、年間の欠席日数が一定を超えると審議の対象となる場合があり、受験において不利になる可能性は否定できません。
ですが、希望を捨てないでください。ICT教材を活用して出席扱いが認められれば、この欠席日数の問題をクリアできる可能性があります。学習の成果を定期テストや提出物で示し、それが評価に反映されれば、内申点への影響を最小限に抑え、お子さんの進路の選択肢を守ることにつながるのです。
「勉強が分からなくなった」子どもの意欲が低下する悪循環
不登校が続くと、当然ながら学校の授業はどんどん先に進んでしまいます。お子さん自身が「もう授業についていけない」「勉強が分からなくなった」と感じ始めると、学習意欲はさらに低下し、学校復帰へのハードルも上がってしまうという、本当に辛い悪循環に陥りがちです。
この問題に対し、多くのICT教材は、学年に関係なく自分のペースで学び直せる「無学年式」のカリキュラムを採用しています。例えば、小学校の基礎からでも、つまずいた単元からでも、誰の目も気にせずやり直せる環境が、お子さんの「分かった!」という小さな成功体験を生み、失いかけていた自信と学習意欲を取り戻す、大切なきっかけになるかもしれません。
相談相手がいない…一人で抱え込みがちな保護者の孤独感
「夫は仕事で忙しく、なかなか相談できない」「同じような悩みを持つママ友もいない…」そんなふうに、一人で全ての不安を抱え込んでいませんか。まるで自分だけが、暗い海にぽつんと取り残されたような孤独感。お子さんのことで頭がいっぱいになり、パートや家事との両立で心身ともに疲れ果ててしまう方も少なくありません。
だからこそ、知ってほしいのです。ICT教材の中には、教材の提供だけでなく、保護者へのサポート体制が充実しているものも多く存在します。専門のカウンセラーや「コーチ」が、学習計画の相談だけでなく、学校との連携方法についてアドバイスをくれることも。こうした第三者のサポートは、孤独な戦いを続ける保護者にとって、本当に心強い味方となってくれるはずです。
出席扱い認定のために。我が子に合う教材選び3つのコツ

とはいえ、制度があると分かっても「じゃあ、何から手をつければいいの?」というのが正直なところだと思います。ご安心ください。ここでは、制度をうまく活用し、お子さんの学習を軌道に乗せるための教材選びの重要なポイントを3つに絞って解説します。このコツを押さえることが、成功への近道です。
自治体のガイドラインを確認しよう!地域ごとのルールの違い
文部科学省が大きな方針を示してはいますが、「出席扱い」の最終的な判断は、在籍する学校の校長先生に委ねられています。そして、その判断の基準となる、より具体的なルールを各市町村の教育委員会が「ガイドライン」として定めていることが多いのです。
まずは、お住まいの地域の教育委員会のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりして、どのような条件が定められているかを確認することから始めてみてはいかがでしょうか。例えば、対面指導の頻度(「月1回以上」など)や、必要な書類が具体的に示されている場合があります。この地域ごとのルールを把握することが、教材選びと学校への相談の、大切な第一歩となります。
学校への相談は戦略的に!交渉を成功させるための準備とは
学校の先生方も日々多忙であり、この制度に詳しくないケースも少なくありません。そのため、ただ「お願い」するのではなく、こちらから具体的な情報や計画を提示し、先生方の負担を減らすという姿勢が、交渉をスムーズに進める上でとても重要になります。
- 文部科学省の通知を提示する: 制度の公的な根拠を示します。
- 自治体のガイドラインを示す: 地域で定められたルールを共有します。
- 利用したい教材の資料を見せる: 学習内容や進捗管理の方法を具体的に説明します。
- 学習計画の案を提出する: 「1日〇ユニット進める」など、出席認定の明確な基準を提案します。
特に、学習時間や進捗状況を客観的なデータとして記録・提出できる機能は、先生方の理解を得る上で、何よりの説得材料になります。「学校への報告しやすさ」も教材選びの重要な視点です。
学習の遅れを取り戻す「無学年式」という選択肢を検討しよう
不登校のお子さんの多くは、学習の遅れに大きな不安を感じています。学年ごとにカリキュラムが決まっている教材だと、「今の学年の内容が分からないのに…」と、かえってプレッシャーを感じてしまうかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、学年の枠にとらわれず、さかのぼり学習や先取り学習が自由にできる「無学年式」の教材です。お子さんがつまずいている根本の原因(例えば、中学校の数学が分からない原因が小学校の分数にある、など)まで戻って、自分のペースで着実に基礎を固めることができます。この個別最適化された学習こそが、自信を取り戻す最短ルートになるのです。
サポート体制は万全?親子で挫折しないための重要項目
自宅での学習を継続するには、お子さん本人の意志はもちろん、保護者のサポートも不可欠です。しかし、親子だけではどうしても行き詰まってしまうこともありますよね。だからこそ、教材提供会社のサポート体制が非常に重要になります。
以下の点をチェックしてみてはいかがでしょうか。
| チェック項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 学習サポート | 分からない問題を気軽に質問できるか?学習計画の相談に乗ってくれるか? |
| 保護者サポート | 学校との交渉方法など、制度利用に関するアドバイスをもらえるか? |
| メンタルサポート | 子どもを励まし、やる気を引き出すような温かい声かけをしてくれるか? |
教材の機能だけでなく、困った時に頼れる「人」の存在があるかどうか。これが、親子で挫折せずに学習を続けるための、何より大切な鍵となります。
【実績多数】出席扱いになる中学生向けICT教材おすすめ5選

ここからは、いよいよ具体的な教材を見ていきましょう。たくさん選択肢があると、かえって迷ってしまいますよね。そこで、不登校のお子さんの学習支援において、実際に出席扱いとして認められた実績が豊富にある、信頼できるICT教材を5つに絞ってご紹介します。大切なのは「お子さんの性格や学習状況に合っているか」です。それぞれの違いを比較しながら、最適な選択肢を見つけていきましょう。
① すらら|1,700人以上の実績と手厚いコーチが魅力

「すらら」は、不登校支援に特に力を入れているオンライン教材で、出席扱い制度の利用を検討するなら、まず最初に候補に挙げるべきサービスです。最大の強みは、1,700人以上(2024年6月時点)という圧倒的な出席扱い認定の実績と、それを支える温かいサポート体制にあります。
- つまずきの原因まで戻れる「無学年式」で、基礎から着実に学び直せる。
- 現役塾講師などの「すららコーチ」が学習計画から保護者の悩みまで親身にサポート。
- 学校へ提出しやすい詳細な学習データ管理機能が、出席認定の交渉を後押し。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(月額・税込) | 3教科: 8,228円 / 5教科: 10,428円(4ヶ月継続コースの場合) |
| 対応教科 | 国語, 数学, 英語, 理科, 社会 |
| 学習スタイル | オンライン学習(PC・タブレット) |
| サポート体制 | 専属の「すららコーチ」による学習設計・進捗管理・保護者サポート |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
② 進研ゼミ中学講座|大手ならではの安心感と豊富な情報量

通信教育の最大手であるベネッセが提供する「進研ゼミ中学講座」も、出席扱い制度に対応しています。長年の教育ノウハウと豊富なデータに基づいた教材は、学校の授業に沿って学習を進めたいお子さんにとって、心強い味方です。
- AIが個人の理解度に合わせた学習プランを提案し、効率的に学習を進められる。
- オンラインライブ授業や「赤ペン先生」の添削指導など、多様な学習スタイルが魅力。
- 豊富な受験情報や進路相談など、大手ならではの充実したサポートが受けられる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(月額・税込) | 中学2年: 8,290円(ハイブリッドスタイル) |
| 対応教科 | 9教科対応(主要5教科+実技4教科) |
| 学習スタイル | 専用タブレット+紙教材 |
| サポート体制 | 赤ペン先生の添削、オンラインでの質問、進路相談など |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
③ 天神|インターネット不要で集中できるオーダーメイド教材
「天神」は、インターネット接続が不要な、買い切り型のデジタル教材です。USBメモリをパソコンに挿して使用するため、ネット環境に左右されず、ゲームや動画などの誘惑を断ち切って勉強に集中させたいご家庭には、ぴったりの選択肢かもしれません。
- 学校で使っている教科書に完全準拠した内容をオーダーメイドで購入できる。
- インターネットを使わないため、有害サイトへのアクセスの心配がない。
- 問題を印刷して紙で学習することも可能で、デジタルとアナログを両立できる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 要資料請求(学年・教科ごとのオーダーメイドプラン) |
| 対応教科 | 国語, 数学, 英語, 理科, 社会 |
| 学習スタイル | PC教材(インターネット不要) |
| サポート体制 | 電話・メールによる学習相談 |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
④ デキタス|大手進研塾が運営する分かりやすい授業が特徴

「デキタス」は、個別指導塾などを運営する城南進研グループのオンライン教材です。塾ならではの「分かりやすさ」を追求した、1回5分程度のコンパクトな授業動画が特徴で、集中力が続きにくいお子さんでも楽しく学習を始められます。
- キャラクターが登場する楽しい授業動画で、学習への抵抗感を和らげる。
- 教科書に沿った内容で、学校の授業の予習・復習がしやすい。
- 比較的リーズナブルな料金設定で、始めやすいのも嬉しいポイント。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(月額・税込) | 中学生: 5,280円 |
| 対応教科 | 国語, 数学, 英語, 理科, 社会 |
| 学習スタイル | オンライン学習(PC・タブレット) |
| サポート体制 | オンラインでの対面指導(デキタス先生)※別途オプションの可能性あり |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
⑤ サブスタ|学習計画の作成まで任せられる伴走型サービス

「サブスタ」は、お子さん一人ひとりに合わせた学習計画をプロが作成してくれるのが最大の特徴です。保護者の方が「何から手をつけていいか分からない」という場合に、学習のペースメーカーとして頼りになるサービスです。
- プロの学習アドバイザーが毎月、個別の学習計画表を作成してくれる。
- 1ヶ月ごとに「学習進捗レポート」が作成され、学校への報告資料として活用できる。
- 有名予備校講師による、分かりやすい映像授業が視聴し放題。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金(月額・税込) | 中学生: 9,800円 |
| 対応教科 | 国語, 数学, 英語, 理科, 社会 |
| 学習スタイル | オンライン学習(PC・タブレット・スマホ) |
| サポート体制 | 学習アドバイザーによる学習計画作成、進捗レポート作成 |
| 公式サイト | 公式サイトで詳細を見る |
ICT教材の出席扱いについて|保護者のよくある質問

きっと、まだまだ細かい疑問や心配事がたくさんあることでしょう。ここでは、多くの保護者の方がつまずきやすいポイントをQ&A形式で解消していきますね。
Q. 1日何時間勉強すれば出席扱いになりますか?
全国で統一された「1日〇時間」という明確な基準はありません。これは、最終的に学校長の判断に委ねられているためです。
一般的には、1授業時間(中学校であれば約50分)が目安とされることが多いですが、学校との話し合いによって個別にルールを決めることになります。例えば、「すらら」を利用しているご家庭では、「1日に3ユニット完了したら出席1日分とする」といった、時間ではなく学習の達成度を基準にするケースも多く見られます。大切なのは、学校側が管理しやすく、お子さんも無理なく続けられる客観的な基準を一緒に作ることです。
Q. 学校が非協力的な場合はどうすればいいですか?
残念ながら、すべての学校がこの制度に詳しいわけではなく、相談しても前向きな返事がもらえないこともあります。これは、多くの保護者の方が直面する、本当に大きな壁です。
そのような場合は、感情的にならず、客観的な資料を基に冷静に情報提供するという姿勢が大切です。
- 文部科学省の公式通知(ウェブサイトから印刷できます)
- お住まいの自治体の教育委員会のガイドライン
- 利用したい教材の学校向け説明資料(「すらら」などは用意されています)
これらを提示しても話が進まない場合は、最終手段として、市町村の教育委員会に直接相談するという方法もあります。
Q. 基礎から学び直すため下の学年の内容でも大丈夫?
はい、全く問題ありません。むしろ、それは制度の趣旨に合致した、非常に効果的な学習方法です。
文部科学省が求める要件の一つに「子どもの理解度を踏まえた計画的な学習プログラムであること」とあります。つまり、現在の学年の内容に固執するのではなく、お子さんが本当につまずいている箇所まで戻って学び直すこと自体が「計画的な学習」として認められます。「すらら」や「進研ゼミ」のような無学年式の教材は、まさにこのために設計されており、出席扱いを認められた多くの実績がありますので、ご安心ください。
Q. 費用はどれくらい?教材ごとの料金を比較したい
費用は、ご家庭にとって本当に重要な問題ですよね。今回ご紹介した教材の月額料金(中学生向け)を改めて比較してみましょう。
| 教材名 | 月額料金の目安(税込) | 特徴 |
|---|---|---|
| デキタス | 5,280円 | 比較的リーズナブルで始めやすい |
| 進研ゼミ | 8,290円 | 9教科対応でコストパフォーマンスが高い |
| すらら | 8,228円~ | 手厚い人的サポートが含まれる |
| サブスタ | 9,800円 | 学習計画の作成まで任せられる |
| 天神 | 要資料請求 | 買い切り型で月額費用は発生しない |
月々の料金だけでなく、入会金や専用タブレットの有無、そして何よりお子さんに合ったサポートが受けられるかという点を総合的に判断して、ご家庭の状況に合ったものを選ぶことが大切です。
お子様のペースで大丈夫。ここまで、本当にお疲れ様でした。

ここまで、ICT教材を活用した出席扱い制度について、具体的な方法や教材をご紹介してきました。情報収集も大切ですが、何よりも忘れないでほしいのは、お子さん自身の気持ちとペースです。周りと比べる必要は全くありません。お子さんが安心して、自分らしくいられる道を探すこと、それが保護者にできる最大のサポートだと私は信じています。
改めて確認!我が子に最適な教材を選ぶ最終チェックリスト
最後に、これまでの情報を踏まえて、我が子にとって最適な教材を選ぶための最終チェックリストをご用意しました。このリストを参考に、お子さんと一緒に話し合いながら、最良の選択をしてください。
- □ 学習スタイルは合っているか?(映像授業、ドリル形式、対話型など)
- □ 難易度は適切か?(基礎からやり直せるか、応用問題にも挑戦できるか)
- □ サポート体制は十分か?(質問はしやすいか、保護者への支援はあるか)
- □ 管理機能は十分か?(学習記録が残り、学校へ報告しやすいか)
- □ 費用は予算に合っているか?(無理なく続けられる料金体系か)
不安なのはあなただけじゃない。まずは無料体験から始めよう
一人で悩み、先の見えない不安に押しつぶされそうになっているかもしれません。でも、大丈夫です。今、こうして情報を集め、行動しようとしていること自体が、本当に素晴らしい一歩です。同じように悩み、そして乗り越えてきた家庭はたくさんあります。
多くの教材では、無料体験や資料請求が可能です。まずはお子さんと一緒に、気軽に試してみることから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、お子さんの、そしてご自身の未来を照らす大きな希望の光になるはずです。

