通知表の二重丸、思わず数えて一喜一憂していませんか?実は、その評価には学校や先生による違いもあるんです。
この記事を読めば、数字の向こう側にあるお子さんの確かな成長を見つけるヒントが見つかります。通知表との新しい向き合い方、一緒に探してみませんか?
【まずは結論から】通知表の評価、気になりますよね。二重丸(よくできる)は全体の6〜8割が目安といわれますが、これは絶対ではありません。大切なのは、今の評価が「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体性」の3つの視点で見られていると知ること。数字だけで判断せず、お子さん一人ひとりの頑張りや個性を認め、成長を応援してあげることが何よりのポイントですよ。
小学校の通知表の二重丸の割合はどのくらい?

小学校の通知表の3段階評価の割合
そもそも、クラスの中で「よくできる」はどのくらいの割合なのでしょうか?
小学校の通知表は、主に「よくできる(◎)」「できる(○)」「もう少し(△)」の3段階評価が採用されています。
一般的に、「よくできる」の割合は全体の60%〜80%程度とされていますが、これは学年や地域、学校によって大きく異なります。
例えば、ある小学校の2年生のクラスでは、国語で70%、算数で75%、理科で80%が「よくできる」だった、という具合です。
一方で、別の小学校の6年生のクラスでは国語で60%、算数で65%…といったように、学年が上がるにつれて割合が少し低くなる傾向も見られます。
小学校の通知表で「よくできる」はいくつある?
では、個人で見るとどうでしょうか。
小学校の通知表で「よくできる」と評価される教科の数は、子どもの個人差が大きいのが特徴です。全教科でよくできるを取る子もいれば、一部の教科に偏ってよくできるが付く子もいます。
ある調査によれば、全教科の80%以上で「よくできる」を取るお子さんは、全体の約15%だそうです。30人のクラスなら、だいたい4〜5人という計算になりますね。

◎を全教科でとれる子が15%って、そんな気がする~!
また、一つもよくできるがない子どもの割合は約5%という数字も報告されています。
【2020年度から新基準】通知表の評価、3つの観点とは?
2020年度から通知表の評価基準が新しくなったことをご存じでしたか? 現在は、どの教科も全国共通の「3つの観点」で評価されるようになりました。このポイントを知っておくだけで、通知表の見え方がぐっと変わりますよ。
その3つの観点とは、以下の通りです。
- 知識・技能 各教科の基礎的な知識や技能が、きちんと身についているかを見る項目です。 国語の漢字の読み書きや、算数の計算力などがこれにあたります。「知っている」だけでなく「実際に使えるか」という点まで見られています。
- 思考・判断・表現 覚えた知識や技能を使って、自分なりに考え、問題を解決する力です。 例えば、自分の考えを筋道立てて発表したり、他の人の意見を参考に的確な判断をしたり、といった場面で評価されます。
- 主体的に学習に取り組む態度 学習に対する、お子さん自身の関心や意欲、粘り強さを見る項目です。 授業に積極的に参加しているか、提出物への取り組み方、グループ活動での協調性など、知的好奇心を持って取り組む姿勢が評価されます。
この3観点による評価の大きな目的は、単なる知識の暗記量で判断するのではなく、得た知識を「どう使うか」という活用力や、「自ら学びたい」という意欲を育てることにあります。子どもたちの未来を見据えた評価方法なのです。
下記の本は中学1年生までに身に付けたい勉強の基本がわかりやすく書かれた人気の教育本!
本格的な反抗期がくる前に、基本的な勉強習慣を身に付けさせて高校受験は第一志望に合格しましょう。
一年生の通知表に二重丸がない場合
もし、1年生の通知表に二重丸が一つもなかったら…。親としてはドキッとしてしまいますよね。でも、だからといって過度に心配する必要はないかもしれません。
1年生は、まず小学校生活に慣れることが何より大切な時期。学校によっては、学習面よりも、毎日元気に通い、お友達と仲良くするといった生活面の成長を重視するところも多いからです。
また、二重丸の付け方は担任の先生の方針によっても異なります。少し厳しめに評価する先生もいれば、たくさん褒めて伸ばす方針の先生もいるので、数だけで一喜一憂するのは少し早いかもしれませんね。
むしろ注目したいのは、通知表の所見欄です。そこには「学校で意欲的に取り組んでいるか」「友達と仲良く過ごせているか」など、先生からの具体的なコメントが書かれているはず。数字では見えない我が子の成長を、そこでしっかり確認しましょう。
小学校の通知表の二重丸の割合について

小学校の通知表はあてにならない?
「小学校の通知表なんて、あてにならないよ」という声、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
確かに、通知表の評価は担任の先生の主観に左右される部分もあり、絶対的なものではありません。また、子どもの素晴らしいところは、通知表の評価項目だけでは到底測れないのも事実です。
しかし、通知表が全く無意味かというと、決してそんなことはありません。先生が日々のお子さんの様子を観察して付けているからこそ、家庭では見えない頑張りや成長を発見できる、大切な手がかりでもあるのです。
私の知人のお子さんは、家ではあまり話さないタイプでしたが、通知表の所見で「グループ活動でいつも友達の意見を優しく聞いています」と書かれていて、知らなかった一面にとても感動していました。
ただし、通知表はあくまでも評価の一側面に過ぎません。家庭での様子や習い事など、学校以外の場所での活動も合わせて、お子さんの成長を多角的に見守ることが大切だと言えます。
小学3年生の通知表がオール2の場合
小学3年生の通知表がオール「できる(○)」だったら、どう考えればよいでしょうか。
まず、3段階評価の真ん中である「できる」は、その学年で求められる水準に達していることを意味するので、学習面では概ね良好な状態だと言えます。
ただ、オール「できる」だからと安心してばかりもいられないのが親心。ここから「よくできる」を目指すには、もう一歩進んだ理解力や応用力が求められることになります。
例えば、ただ計算問題が解けるだけでなく、文章題で計算式の意味をしっかり理解したり、少し難しい発展問題に挑戦したりする意欲も評価の対象になるのです。
また、3年生は学習内容が難しくなる時期でもあります。つまずきを早期に発見し、適切なサポートを行うことが大切です。
通知表だけでなく、日々の学習の様子にも気を配りながら、お子さんの理解度を把握してあげたいですね。
ご家庭で手軽にお子さんのつまずきを発見する方法として、Z会の無料お試し教材を活用するのも一つの手です。どの単元が苦手か、ゲーム感覚でチェックできますよ。
通知表がオールよくできるということ
もし通知表がオール「よくできる」だったら、それは学習面で非常に優れた力を持っている証拠です。「よくできる」は、学年の目標を十分に上回る理解力や応用力がある、という評価だからです。
オールよくできるを取るためには、単に知識を暗記するだけでは不十分です。習得した知識を実際の場面で活用したり、さらに発展的な内容に興味を持って学習したりする姿勢が求められます。
ただし、これを絶対的な目標にする必要はありません。お子さんの個性や特性によっては、得意な教科とそうでない教科があるのは自然なことです。
何よりも大切なのは、結果に一喜一憂するのではなく、お子さん一人ひとりの良さを認め、得意なことをさらに伸ばしてあげることだと言えるでしょう。
下記のプランボードは、宿題や忘れ物がなくなると評判の勉強グッズ。

このグッズ1,500円以下で忘れ物が防げるなんて、超便利♪
小学校の通知表が5段階評価になったときの割合

最近では、3段階ではなく5段階評価の学校も増えてきました。その場合、割合はどうなるのでしょうか?
5段階評価の場合、一般的に「A(十分満足できる)」「B(おおむね満足できる)」「C(振り返りを促す)」といった評価が用いられます。(※学校によりD、Eの評価がある場合も)
文部科学省の調査によると、5段階評価を導入している小学校では、各評価の割合は以下のようになっています。
- A:全体の約20%
- B:全体の約50%
- C:全体の約25%
- D:全体の約4%
- E:全体の約1%
この割合を見ると、約半数のお子さんが「B」の評価を受けていることがわかります。「B」は、学習内容をおおむね理解し、授業にも参加できている状態を示します。
一方、最も良い評価である「A」を得るには、学習内容を十分に理解した上で、自ら課題を見つけて学習を深めるような、より主体的な姿勢が求められます。
小学校の通知表は、子どもたちの学校での学習状況や成長を示す重要な指標です。しかし、学習面での評価だけでなく、家庭での学習環境やサポートも大切です!
そこで東進オンライン学校 小学部は、自宅での学習をサポートする理想的な通信教育なのでおすすめ。
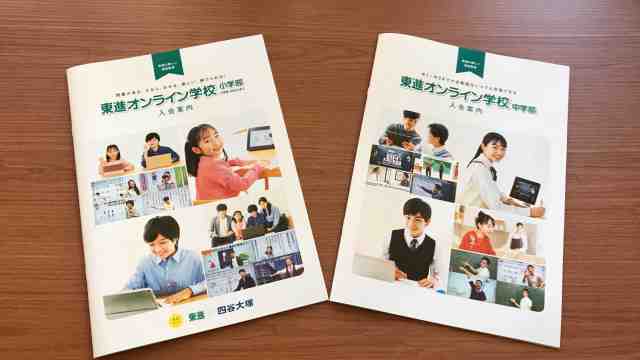
特に「未来発見講座」では、子どもたちが将来の夢を見つけるきっかけを提供します。日本最強の講師陣による授業で、子どもの学力を確実に伸ばすことができます。

東進と四谷大塚がタッグを組んだ通信教育はコレだけ!
小学校の通知表でCの割合はどれくらい?
先ほどのデータによれば、5段階評価で「C」の評価を受けるお子さんは、全体の約25%、つまり4人に1人程度です。「C」は、学習内容の理解が少し不十分で、つまずきが見られる状態を指します。
もし「C」の評価が付いた場合は、まずお子さんの学習状況を丁寧に見てあげることが大切です。つまずきの原因は内容の難しさなのか、それとも取り組み方なのかを、冷静に見極める必要があります。
その上で、家庭と学校が協力して適切な支援を行うことが求められます。具体的には、苦手な部分を一緒に復習したり、学習方法を工夫したり、やる気を引き出すような声かけをしたり、といったサポートが考えられます。
お子さんの特性に合わせたきめ細やかなサポートが、きっと学力の向上につながるはずです。
Q&A:小学校の通知表についてよくある質問
通知表の評価は、本当に信頼できるのでしょうか?
通知表の評価は担任の先生の主観に左右される部分もあるため、絶対的な基準とは言えません。

なんでうちの子がこんな評価なんですかって、担任にクレームを言う方もいますが大丈夫!
しかし、子どもの学校での様子を知る重要な手がかりの一つであることは確かです。
通知表の結果だけでなく、日々の学習や家庭での様子も合わせて、多角的に子どもの成長を見守ることが何より大切です。
オール3(よくできる)を目指すべきでしょうか?
オール「よくできる」を目指すこと自体が目的になってしまうより、お子さん一人ひとりの良さを認め、伸ばしていくことのほうがずっと大切です。
お子さんの個性や特性によって、得意なこととそうでないことがあるのはごく自然なことですから。
通知表の評価に一喜一憂するのではなく、お子さんの興味・関心や学習スタイルに寄り添い、適切な支援を行ってあげたいですね。
通知表の評価が低い場合、どうすればよいでしょうか?
通知表の評価が思ったより低かった場合、まずは慌てずにお子さんの学習状況を丁寧に把握することが第一歩です。
つまずきの原因を見極めた上で、家庭と学校が連携してサポートしていくことが鍵になります。
具体的には、学習内容の復習、やり方の工夫、そして学習意欲の向上など、できることはたくさんあります。お子さんの特性に合わせたきめ細やかなサポートが、学力向上につながるはずです。
まとめ:小学校の通知表の二重丸の割合
この記事では、小学校の通知表について解説しました。二重丸の割合は、学年や地域によって異なりますが、全体の60%〜80%程度がひとつの目安です。
しかし、通知表はあくまでもお子さんの成長の一側面を切り取ったもの。その数字だけで判断せず、多角的に見守ることがとても重要です。
二重丸の数だけにとらわれず、お子さん一人ひとりの個性や良いところに目を向け、それに合わせたサポートをしていくことこそが、健やかな成長につながるのではないでしょうか。
とはいえ、通知表の結果を見て「具体的な対策を考えたい」と思うのが親心ですよね。そんな時は、まずお子さんに合った教材かどうかを無料で試してみるのがおすすめです。
Z会なら、質の高いお試し教材を資料請求だけで手軽に体験できます。我が家で実際に成果が出た方法の詳細は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
- 3段階評価の割合: 「よくできる」は全体の60%〜80%が目安。ただし学校や学年で差が大きい。
- 個人の差: 全教科の8割以上で「よくできる」を取る子は全体の約15%。個人差が大きいのが前提。
- 3つの評価基準: 評価は「①知識・技能」「②思考・判断・表現力」「③主体的に学習に取り組む態度」が柱。
- 1年生の評価: 生活面に慣れることを重視する学校も多く、二重丸がなくても心配しすぎないこと。
- 評価との向き合い方: 通知表は成長を知るための一つの手がかり。担任の先生の観察に基づく大切な記録。
- オール「できる」の場合: 学年相応の力はクリア。より応用的な力で「よくできる」を目指せる段階。
- 5段階評価の場合: 「B(おおむね満足)」が約半数、「C(振り返りを促す)」が約25%を占める。
- 何より大切なこと: 数字に一喜一憂せず、お子さん一人ひとりの良さを認め、成長を応援すること。
関連する研究論文
関連する研究論文
万が一、我が子がトラブルを起こした際の対処方法を知っておきたい方は、子供がトラブルを起こし迷惑をかけた!手紙・お詫び文で謝罪する方法をどうぞご覧ください。



