お子さんが購読中の新聞をなかなか読んでくれず、「このままで大丈夫かしら…」と、心配になることがありますよね。この記事では、そんなお悩みを解決するための小学生新聞の活用法を具体的にご紹介します。親子で楽しく取り組める方法で、お子さんの「知りたい!」という好奇心のスイッチを、そっと押してあげましょう。
【最初にチェック!】
せっかくの新聞を積読にしないための秘訣は、親が少しだけ関わる「楽しい仕組み」を作ること。お子さんのタイプに合わせて、まずは「これならできそう!」と気軽に思えるものから、ぜひ試してみてください。
| こんなお悩みに | おすすめの活用術 |
|---|---|
| 子供が活字に興味を示さない | 親子で一緒に読み、面白い記事を話題にする |
| 語彙力や読解力が心配 | 「天声こども語」の音読や書き写しを試す |
| 時事問題への対策がしたい | 新聞記事のスクラップを週末の習慣にする |
| 勉強っぽくなるのが嫌 | キャスターごっこや辞書引きゲームを取り入れる |
新聞は最高の教材!小学生新聞で「読む力」がぐんぐん育つ
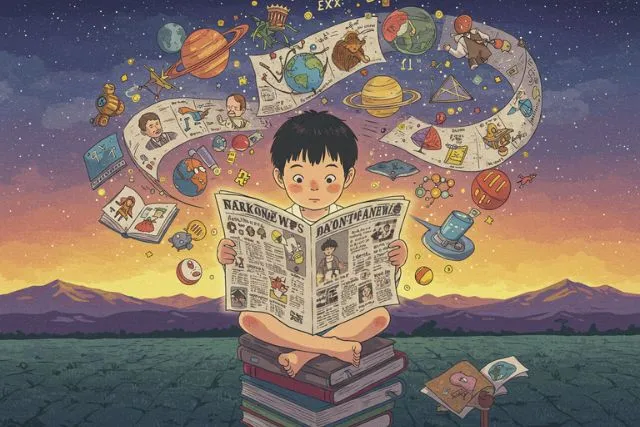
「新聞を読みさえすれば、きっと子どもの力になるはずなのに…」そう信じているからこそ、今の状況がもどかしいのですよね。まずは、新聞が持つ本当の価値を再確認してみましょう。
新聞を「使う」習慣が子どもの未来の選択肢を広げる
小学生新聞は、世の中の出来事を分かりやすく教えてくれるだけではありません。すべての勉強の土台となる「読解力」や「思考力」を育むための、栄養満点な情報がぎっしり詰まっています。実際に、新聞を活用した教育(NIE)は、子供の学力向上に効果があることが日本新聞協会の調査でも報告されているんですよ。
ただ「読む」だけでなく、記事について話したり、書き写したり、調べたり。そんな風に新聞を能動的に「使う」習慣こそが、お子さんの視野をぐっと広げ、中学受験はもちろん、その先の未来を豊かにする大きな力になるはずです。
まずはお母さん、毎日お疲れ様です。そのお悩み、誰にも言えずに一人で抱えていませんでしたか?一つひとつ、気持ちを整理していきましょう。
「うちの子、新聞を全然読まない…」親が抱える共通の悩み3つ

悩み1:月々の購読料が無駄になっている気がして焦る
お子さんのために、と意を決して始めた小学生新聞。それなのに、ポストに真新しい新聞が届くたび、読まれていない先週分が目に入って、思わずため息…。なんてことはありませんか。
月々2,100円(朝日小学生新聞の場合)の購読料は、決して安い金額ではありませんものね。「元を取らなきゃ」と焦るお気持ち、痛いほどよく分かります。でも、その焦りが、かえってお子さんを新聞から遠ざけてしまうこともあるのかもしれません。
悩み2:ゲームばかりで活字離れ…中学受験は大丈夫?
スマートフォンやゲームに夢中になるお子さんの姿は、微笑ましくもあり、ちょっぴり心配でもありますよね。「このままで、活字を読む力がつかないのでは?」という不安、私も常に感じています。特に、中学受験を考え始めると、避けては通れないのが時事問題です。
「新聞に親しんでほしい」と心から願う一方で、具体的に何から手をつければ良いのか分からない。多くの保護者の方が、同じように感じています。
悩み3:「読みなさい!」とつい言ってしまう自己嫌悪
「新聞、読んだの?」という声かけが、いつの間にか「勉強になるんだから、読みなさい!」という強い口調に…。そして、お子さんの浮かない顔を見て、後から自己嫌悪に陥ってしまう。
私も昔、「早くしなさい!」と言った後で、子供の悲しそうな顔を見て、夜中に一人で反省会を開いたことが何度もあります。お子さんのためを思えばこそ、つい言ってしまうんですよね。でも、大丈夫。少し視点を変えるだけで、明日からの声かけがきっと変わります。
親子で楽しく挑戦!子供新聞を使いこなす具体的活用術7選

もう「読みなさい」は言わなくて大丈夫。ここからは、お子さんが「ちょっと見せて!」と自ら新聞を手に取りたくなるような、具体的な7つの作戦会議を始めましょう!
活用術1:「すごいね!」親の一言で子どものやる気が変わる
まず、最も大切で、そして最も効果的な方法があります。それは、保護者の方も一緒に新聞を楽しむことです。お子さんだけに「はい、どうぞ」と渡すのではなく、まずはお父さん、お母さんが楽しそうにページをめくってみてください。
そして、「この記事面白いよ!」「こんなことがあったんだって、すごいね!」と、見つけた発見をお子さんにシェアするのです。親が楽しんでいる姿を見せること、そしてお子さんが記事を読んだ時に「へぇ、そんなこと知ってるんだ!すごいね!」と驚き、褒めてあげることが、何よりのモチベーションになります。
活用術2:「天声こども語」の音読・書き写しで語彙力アップ
朝日小学生新聞の名物コラム「天声こども語」は、語彙力と文章力を鍛えるのにうってつけの教材です。まずは一日一回、親子で音読することから始めてみてはいかがでしょうか。声に出して読むことで、文章の心地よいリズムや言葉の響きを、体で覚えることができます。
慣れてきたら、お気に入りのノートを「書き写し専用ノート」にするのもおすすめです。プロが書いた良質な文章を丁寧に書き写す体験は、自然と正しい日本語の「型」を身につける手助けとなります。
| 取り組み方 | ポイント |
|---|---|
| 音読 | 親子で交代で読むのも楽しい |
| 書き写し | 専用ノートを使うと達成感がアップ |
| 語句調べ | 分からない言葉はマーカーを引き、一緒に辞書で調べる |
活用術3:キャスターごっこで楽しく時事ニュースに親しむ
「ニュースあれこれ」のような時事ニュースのコーナーは、少しお堅いイメージがあるかもしれませんよね。そんな時は、「ニュースキャスターごっこ」で雰囲気をガラリと変えてみましょう。
お子さんにキャスター役をお願いし、記事をニュース原稿に見立てて読んでもらうのです。少し大げさなBGMを流してみたり、おもちゃのマイクを用意したりすると、さらに本格的に。楽しみながらニュースを読むことで、難しい内容もスッと頭に入ってきやすくなりますよ。
活用術4:週末は親子で挑戦!新聞スクラップノートを作ろう
新聞スクラップは、思考力や表現力を養うのにぴったりの活動です。週末の時間などを利用して、親子で世界に一つだけのスクラップノート作りに挑戦するのも楽しいですよ。
難しく考える必要はありません。1週間分の新聞の中から、お子さんが「面白い!」と感じた記事を一つ選んで切り抜き、ノートに貼るだけ。そしてその下に、一言感想を書くことから始めましょう。うちの子は最初、好きなサッカーチームの記事ばかりでしたが、いつの間にか宇宙や環境問題の記事も集めるようになって、成長に驚かされたものです。
準備するもの: ノート、はさみ、のり
- STEP1: 好きな記事を1つ選んで切り抜く
- STEP2: ノートに貼り、日付と新聞名を書く
- STEP3: 記事の感想や、思ったことを一言書く
活用術5:「知りたい!」を引き出す楽しい辞書引きゲーム
新聞を読んでいると、どうしても分からない言葉が出てきます。そんな時、「また難しい言葉…」と諦めてしまうのはもったいない。辞書や図鑑をリビングのすぐ手に取れる場所に置き、「知らない言葉探しゲーム」をしてみませんか?
ルールは簡単。「この記事の中から、知らない言葉を3つ見つけよう!」と声をかけ、見つけたら一緒に辞書で意味を調べるだけ。「なるほど!」と分かる瞬間を親子で共有できる、とても嬉しい時間になります。
活用術6:無料ワークシートを印刷して学習効果を最大化する
新聞社によっては、記事の内容と連動した無料の学習ワークシートを公式サイトで提供している場合があります。(例:読売新聞の「読売ワークシート通信」など)
こうした教材を上手に使えば、記事を読んだ後の理解度チェックや、関連知識の深掘りがスムーズにできます。「読みっぱなし」にせず、クイズ形式で復習することで学習効果がぐんと高まるので、週末の学習習慣としてもおすすめです。
活用術7:かさばる新聞の最適な保管方法と整理のコツ
日刊の新聞は、対策しないとあっという間に溜まってしまい、置き場所に困ることもありますよね。そんな時は、簡単な保管のルールを決めてしまいましょう。
一番手軽なのは、100円ショップなどで手に入るA4のクリアファイルを活用する方法です。スクラップしたい記事や、後で読み返したい特集だけを切り抜いてファイルに入れていく。そして、それ以外の部分は1週間分たまったら処分する、と決めておけば、お部屋が新聞でいっぱいになるのを防げます。
始める前にスッキリ解決!新聞活用に関するよくあるQ&A

新しいことを始める前は、色々な疑問が浮かびますよね。一つひとつ、一緒に解消していきましょう。
Q. マンガしか読まないのですが、それでも意味はありますか?
はい、もちろん大いに意味があります。 まずは新聞を毎日手にとって開く、という習慣がつくこと自体が、素晴らしい第一歩です。
多くの新聞には、歴史や科学をテーマにした質の高い学習マンガが掲載されています。マンガを入り口にして、少しずつ他の記事にも興味が広がっていくケースは本当に多いんですよ。焦らず、お子さんの「好き」という気持ちを、まずは応援してあげてください。
Q. 読売と朝日、どちらがスクラップ学習に向いていますか?
どちらの新聞にも良さがありますが、お子さんのタイプや目的によって向き不向きがあります。
- 読売KODOMO新聞(週刊): オールカラーで写真や図が多く、記事が四角くレイアウトされていることが多いのが特徴です。そのため、見た目にも楽しいスクラップノートが作りやすく、新聞活用が初めてのお子さんにぴったりです。
- 朝日小学生新聞(日刊): ニュースの背景を深く掘り下げた記事や、中学受験を意識した内容が豊富です。特定のテーマ(環境問題、国際情勢など)をじっくり探求するようなスクラップ学習に適しています。
Q. 忙しくて毎日付き合う時間がありません。どうすれば?
お仕事や家事で忙しい中、毎日付き合うのは本当に大変ですよね。ご安心ください。大切なのは時間の長さよりも「親子で関わる習慣」そのものです。
平日は「一面の見出しだけ一緒に確認する」「面白そうな記事に付箋を貼っておいてあげる」といった簡単な関わりに留め、週末に15分だけ、一緒にスクラップをする時間を設けるなど、ご家庭の生活スタイルに合わせた無理のない計画を立てることが、長続きの秘訣です。
Q. 書き写しは大変そうですが、効果的なやり方はありますか?
確かに、長い文章をすべて書き写すのは大人でも大変です。まずは「自分が一番心に残った一文だけを書き写す」ことから始めてみましょう。
大切なのは、完璧を目指すことではありません。プロが紡いだ良質な文章に、そっと触れる機会を増やすことです。たった一文でも、丁寧に書き写すことで、言葉の使い方が自然と身についていきます。慣れてきたら、少しずつ量を増やしていくのがおすすめです。
中学受験を考えるなら「朝日小学生新聞」が強い味方に

ここまで様々な活用法をご紹介してきましたが、「うちの場合は、中学受験が一番の心配事なの」という方もいらっしゃると思います。もしお子さんの中学受験を少しでも視野に入れているのであれば、「朝日小学生新聞」の活用は非常に心強い選択肢になります。
この記事で紹介した「天声こども語」の書き写しや、「ニュースあれこれ」を使った時事問題対策は、多くの受験生が実践している王道の学習法です。日々のニュースに触れる習慣そのものが、入試で問われる社会への関心や思考力をじっくりと育みます。購読を迷っている方も、すでにお手元にある方も、ぜひ一度、受験という視点で紙面を見直してみてはいかがでしょうか。お子さんの未来を切り拓くヒントが、きっと見つかるはずです。
▼中学受験にも強い!朝日小学生新聞の詳細はこちら
朝日学生新聞社 公式サイトで確認する
まとめ:新聞は最高の家庭学習!まずは親子の対話から
ここまで、たくさんの活用法をご紹介してきました。最後に、一番大切なことをお伝えしますね。
「読みなさい」から「これ知ってる?」への転換
子供新聞の活用は、「勉強させなきゃ」という保護者の方の気持ちが強いと、なかなかうまくいかないものです。一番の秘訣は、新聞を「親子の会話を広げるための、ちょっと特別なツール」と捉え直すことかもしれません。
「これを読みなさい」という一方的な指示ではなく、「この記事にこんなことが書いてあったよ、どう思う?」と、対話のきっかけとして新聞を使ってみてください。
まずは1日10分、親子で新聞を開く習慣から
最初から完璧を目指す必要は、全くありません。まずは1日10分で良いので、親子で一緒に新聞を開いてみることから始めてみましょう。
その10分の積み重ねが、お子さんの知的好奇心に火をつけ、将来の可能性を大きく広げるはずです。この記事が、そのための第一歩を踏み出すささやかなきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
この記事で紹介した方法の中で、「これならできそう!」と思えるものは見つかりましたか?まずは週末に、お子さんと一緒にスクラップノート作りから挑戦してみてはいかがでしょうか。

